日本の学校 冬の風物詩・なわとび
-体の使い方の基礎は-1・2歳で決まる-(下部小さく/白文字-or-グレー文字)-ー最初の習い事に体操教室が最適な理由-3.png)
― “引っかかったら座りましょう” の光景から考える ―
先日、ある小学校の授業参観に伺いました。
校庭では、子どもたちがなわとびをしていました。
先生の声が響きます。
「引っかかった人は座ってください」
最初は20人以上が元気に跳んでいたのに、
1分も経たないうちに半分以下に。
引っかかった子たちは、その場にぺたんと座って待つことになっていました。
中には暇を持て余して砂いじりを始める子も。
跳べる子はずっと跳び続け、
跳べない子は練習する機会すら与えられない。
見学していた保護者の方々の表情が、
だんだん曇っていくのがわかりました。
「授業参観に来たのに、我が子が座って待っているだけ。」
「何のために来たんだろう…」
そう感じた方もいたのではないでしょうか。
座って待つ時間、あの子はどんな気持ちだったのか
授業参観だけではありません。
普段の体育の時間でも、同じことが起きています。
周りの子は跳んでいるのに、自分だけ引っかかる。
座って待つように言われて、することもなく時間が過ぎていく。
先日、私の教室に来てくれた小学2年生の女の子も、
「いつも一番最初に引っかかって座る側なんです」と話してくれました。
これまでの授業の時間、この子がどんな気持ちでいたのかと思うと、
胸が締めつけられるようでした。
たった1時間で世界が変わった
そのお子さん、前跳び1回しか跳べなかったのが、
たった1回のレッスン(50分)で 連続10回 跳べるようになりました。
レッスン後、お母様がおっしゃった言葉が忘れられません。
「1時間前が嘘のようです」
やったことはとてもシンプルです。
縄の長さを整え、手首の動きを少し修正し、
跳ぶタイミングをつかむコツを伝えただけ。
お子さんの「できた!」という笑顔と、
それを見つめるお母様の涙が、何よりのご褒美でした。
「跳べない」のは、その子のせいではありません。
ただ、正しい方法を教えてもらえる機会がなかっただけ。
なぜ学校の授業では上達しにくいのか
「引っかかったら座りましょう」という指導法には、構造的な問題があります。
- 跳べる前提の授業になっている
- 跳べない子ほど練習時間が減っていく
- どこを直せばいいのか教えてもらえない
- ただ座って待つだけの時間が続く
- できる子とできない子の差が広がっていく
これは先生のせいではなく、集団授業の仕組み上の限界でもあります。
一人の先生が30人全員を見ながら、
それぞれに必要な修正点を伝えるのは難しいのです。
でも、その結果として
「苦手なまま学年が上がる子」や
「体育の時間が嫌いになる子」が生まれてしまいます。
本当に必要なのは「できるようになる時間」
なわとびが苦手な子に必要なのは、
「座って待つ時間」ではありません。
- なぜ引っかかるのか、一緒に原因を探す
- その場ですぐに修正ポイントを伝える
- 小さな成功体験を積み重ねる(1回 → 3回 → 5回 → 10回)
- 「できない」で終わらせず、「できた!」で終わる
実は、ほんの少しのポイント(縄の長さ・手首の使い方・タイミング)を変えるだけで、
誰でも驚くほど跳べるようになります。
学校では時間的に難しいその「見極めと修正」を、
個別レッスンでは丁寧に行うことができます。
冬休みはチャンスです
もうすぐ冬休み。
新学期の体育を楽しみに迎えるために、
「できない」を「できた!」に変えられる絶好の時期です。
寒い冬の校庭で、跳べる子をうらやましそうに見ていたあの子が、
春には笑顔で跳んでいる——。
そんな瞬間を、一人でも多くの子に届けたいと思っています。

-体の使い方の基礎は-1・2歳で決まる-(下部小さく/白文字-or-グレー文字)-ー最初の習い事に体操教室が最適な理由-1-140x96.png)
-体の使い方の基礎は-1・2歳で決まる-(下部小さく/白文字-or-グレー文字)-ー最初の習い事に体操教室が最適な理由-4-140x96.png)
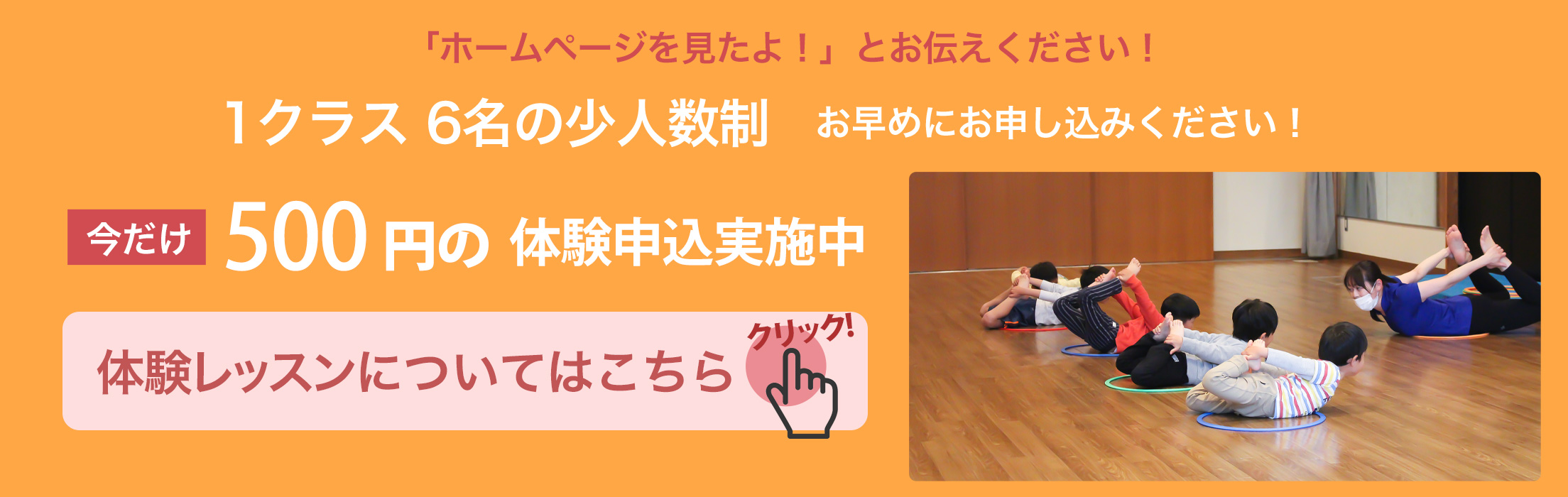
LEAVE A REPLY